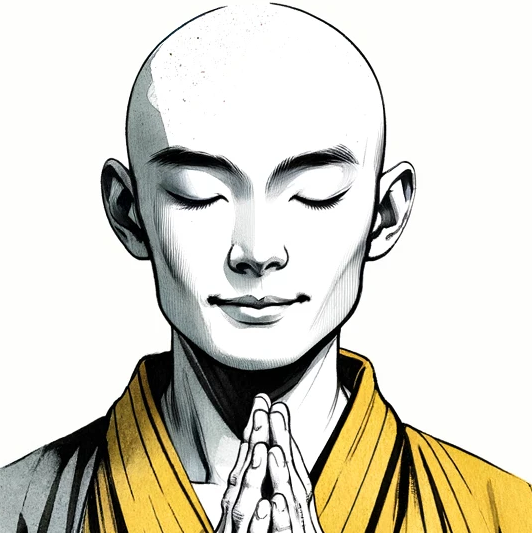朝、目が覚めたのに、体が動かない。
布団から出ることが、こんなにつらい日があるとは思わなかった・・・
そんな自分を、「ダメだ」と責めてしまう声が、心の中に響くことがあるかもしれません。
でも、どうか覚えていてください。
それは「弱さ」ではなく、心が、あなたを守ろうとしているサインなのです。
脳科学が示す「動けない朝」のメカニズムとは
脳科学の研究では、強いストレスを感じたとき、人の「やる気」や「集中力」をつかさどる部分がうまく働かなくなることがわかってきました。
つまり、「怠けている」のではなく、「心と脳がそっとブレーキをかけている状態」なのです。
それは、自分の限界を超えないようにと、身体が教えてくれている優しいサインです。
まずは、その静かなメッセージに気づいてあげましょう。
仏教が教える「今のままの自分を受け入れる力」
仏教には「如実知見(にょじつちけん)」という言葉があります。
それは、「ありのままを見て、あるがままに受けとめる」という意味です。
苦しみの中にいるとき、人はどうしても「こうでなければ」と自分を責めてしまいます。
でも、動けないあなたも、決して間違っていません。
今ここにいるそのままの姿が、すでに尊い存在なのです。
禅では、ただ座る修行「只管打坐(しかんたざ)」があります。
何かを成し遂げなくても、ただ座ること、それだけで十分に意味があるとされています。
「何もできない日」こそ、心が回復している証
現代では、「動くこと」や「結果を出すこと」が正解のように思われがちです。
でも、植物も冬には動きを止め、静かに春への準備をしています。
人の心も同じです。
動けない時間は、内側で次の一歩を準備している大切な時間なのです。
「今日は何もできなかった」と思う日こそ、心の奥では静かな力が育っているのかもしれません。
気分が沈む朝にできる、心を整える3つの習慣
では、動けない朝に、どんな過ごし方があるのでしょうか?
簡単にできる3つのことをご紹介します。
呼吸を数える「数息観」で心を整える
ゆっくりと息を吸って、吐く。
その呼吸に数字を添えてみてください。
「1、2・・・」と数えるだけでも、心が少し静まります。
これは「数息観(すそくかん)」という、禅の修行の一つです。
五感に気づく「サティ」の実践
布団の温かさ、朝の光、聞こえる音…
今ある感覚に静かに目を向けてみてください。
これは「気づき(サティ)」という仏教的な心の訓練です。
自分の存在を確かめる、小さな行為
手を胸に当てる。
お茶を淹れる。
それだけでも、自分の存在を再確認できます。
小さな動きが、心に安心を灯してくれます。
自分に優しくすることが、回復の第一歩になる理由
つらい朝に必要なのは、「変わらなければ」という焦りではなく、「今を認める」やさしさです。
あなたが感じている苦しみは、きっと誰かの痛みともつながっていて、あなたが自分に優しくできたとき、誰かにも優しくなれるはずです。
動けない朝も、大丈夫。「今ここ」にいるあなたへ
それは、がんばりすぎた心が「ちょっと休もう」と語りかけている時間です。
誰かと比べなくていい、昨日の自分と比べる必要もありません。
お釈迦様はおっしゃいました。
「今の自分をあるがままに見よ」
あなたが今日ここにいること、それはもう、十分に価値あることです。
明日、少しだけ歩き出せたら、それでいい。
今日のあなたに、どうかやさしくあってください。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
ー合掌ー